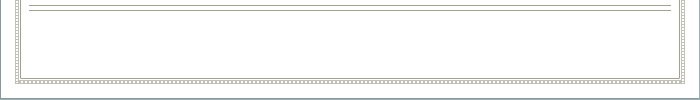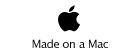研究内容

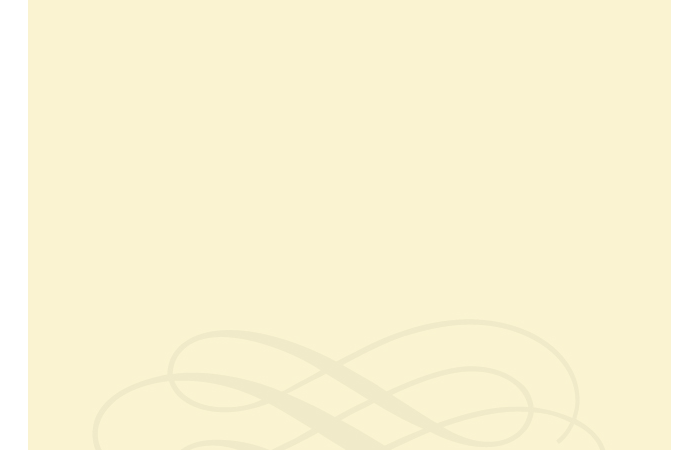
海には約20万種の生き物(魚を含む)が住んでいますが、その98%は生涯あるいは一時的にせよ海底とのつながりをもち、ベントス(底生生物)と呼ばれています。海底は水中と異なり、その生息環境は多様であり、これが多くの生き物を育む要因となっています。このようなベントスの生態を明らかにするのが、私の一貫した研究テーマです。
近年、陸域での工業化や人間活動の高まりによって、海に多くの有機物が流入し, "海がよごれる"といった深刻な事態がおきています。有機物は海の生態系に組み込まれて、大部分は海の恵みとして漁獲されますが、一部は沿岸の海底に沈み、人間活動とは一見、無縁な泥場の停滞域がいたるところに出現しています。このような富栄養化が進行すると、正常な自然界の物質・エネルギー循環が破壊されて、海面では赤潮が発生したり、海底では逆に生き物が衰退するので、"海がよごれる"のは悪いのだというイメージだけでとらえがちですが、それは間違いです。
私の研究成果によると、富栄養化も一段とすすむと それまでとは異なった生き物にとって替わられ、泥場の海底がにぎやかになってくるようです。ベントスの数量、種類数、多様性のどれをとっても、砂場の正常域とくらべて劣っていません。ただ、動物の生命維持に欠かせない酸素が、堆積有機物の分解・消費によって海底近くでは少なくなり、この点は困ったものです。

福山市田尻人口干潟での調査風景
一方、正常域を代表する砂場の干潟は、埋め立てやコンクリート護岸の設置によってこの60年間で半数が消失してしまいました。
そこは食用として大切なアサリのすみ場所ですが、このような乱開発によって近年のアサリ激減といった憂き目にあいました。何とかしなければなりません。その方策として、海砂や浚渫土さらに建設用骨材を投入することで、人工干潟をつくることが最近注目されています。このような海底基盤の変化に伴ってアサリ以外のベントスも大きく変貌せざる得ない状況にあります。
以上のように、人工的に創出された劣悪な海底環境でもたくましく生きる術をもっているベントスの生残戦略を、主に浮遊幼生の着底・変態期にみられる個体群動態から研究しています。