研究内容
I.概要
研究課題:「シトクロムcの作用機構の解明とその利用」
研究目標1:分子構造「シトクロムcの分子構造と熱力学的性質を明らかにする。」
研究目標2:分子生成「シトクロムcの生合成の過程を明らかにする。」
研究目標3:分子機能「シトクロムcの電子伝達反応の機構を明らかにする。」
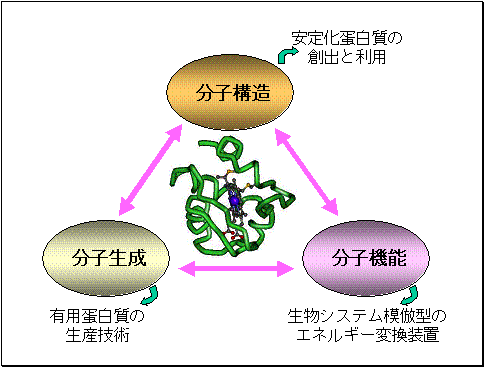
研究の概念図: 三つの研究目標は、相互に関連しあっている。さらに、それぞれの目標を出発点として目指すべき応用研究を示す。
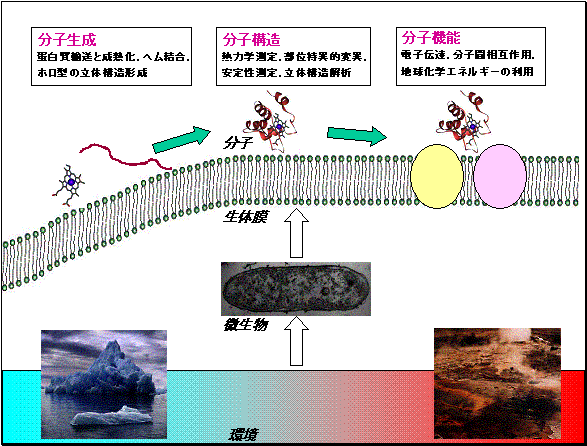
研究の全貌: 多様な環境から得られる微生物に普遍的に備わる電子伝達系の蛋白質シトクロムcに着目し、環境から分子までの幅広い階層性にわたる研究を展開する。
II.研究内容の説明
研究の理念
「電子伝達蛋白質シトクロムcの作用機構を明らかにし、生物が生きていくのに必要なエネルギーを得るしくみを理解する。さらに、有用蛋白質の創出技術と生物にならうエネルギー変換装置の構築を目指す。」
生物が生きていくにはエネルギーを必要とする。生物のエネルギー代謝の問題は、「生命とは何か?」といった問いかけでもある。
生体内でのエネルギー代謝の過程を化学反応としてとらえる場合、それは電子の授受を行う低分子化合物や蛋白質の機能に依存していると言える。微生物から植物や動物に至る多くの生物がもつシトクロムcは、エネルギー代謝に必須な電子伝達蛋白質である。
私たちは、様々な生物がもつシトクロムcの分子構造と物理化学的性質の関係を起点に、細胞内でのシトクロムcの生合成の過程や電子伝達のしくみを明らかにしようとしている。以下に示す三つの研究目標を達成することで、生物がエネルギーを得るために必要なシトクロムcの役割を明らかにする。加えて、工学系に利用できる高い安定性をもつ蛋白質の創出とその生産技術の確立、さらには生物システム模倣型のエネルギー生産を目指すバイオテクノロジーの基盤を築く。
研究目標1:分子構造
「シトクロムcの分子構造と熱力学的性質を明らかにする。」
蛋白質は、その立体構造を保持してはじめて本来の役割を果たすことができる。したがって、蛋白質の構造は、その機能を知るための必要不可欠な情報である。
「研究目標1」では、シトクロムcが自身の立体構造をどのように保持するのかについて、熱力学的解析により定量化する。様々な温度環境に生育する微生物から相同性の高いシトクロムcを単離し、それらの安定性と立体構造を比較する。ヒトが住めないほどの極限高温環境で生育する微生物から得られたシトクロムcは、常温に生息する微生物のものより高温で安定なのかなど、蛋白質の安定性が微生物の生育温度に対応しているかどうかを調べる。このように、様々な微生物のシトクロムcの共通点や相違点を見つけ、部位特異的変異導入実験によって、安定性と構造の関係を明らかにする。
また、高温、低温のみならず、地底や海底など他の極限環境に生息する微生物の蛋白質にも研究の材料を求め、生物が過酷な環境に耐えるための分子戦略機構を明らかにする。以上の研究から予想される成果を、産業レベルで適用可能な安定化蛋白質を創出するための技術基盤を確立する。
研究目標2:分子生成
「シトクロムcの生合成の過程を明らかにする。」
エネルギー代謝経路において電子伝達の機能を担うシトクロムcがその役割を果たすには、成熟化したホロ型蛋白質が細胞内のしかるべき場所に存在していなければならない。すなわち、シトクロムcを構成するポリペプチド鎖とヘムが細胞内でそれぞれ合成された後、両者が結合し、細胞膜上に運ばれる必要があるということである。したがって、シトクロムcの作用機構を理解するためには、細胞内でどのような過程を経て合成されてくるのかといった蛋白質構造形成の歴史を知ることも重要である。
「研究目標2」では、遺伝学の手法を駆使し、細胞レベルでの現象を観察することから細菌シトクロムcの生合成に必要な分子装置を明らかにする。材料とするシトクロムc蛋白質は、「研究目標1」でも用いられている。すなわち、蛋白質生合成の問題に、基質である蛋白質の熱力学の観点を取り入れた全く新しい切り口から研究を展開する。このような研究から得られる成果は、シトクロムcに限らず広く一般の蛋白質の細胞内生成や構造形成に関する知見を提供するはずであり、それを有用蛋白質の大量生産技術に適用する。
研究目標3:分子機能
「シトクロムcの電子伝達反応の機構を明らかにする。」
シトクロムcの機能は、生体膜上で電子を運ぶことである。多様な生育形態をもつ微生物は、シトクロムcが他の電子伝達蛋白質と相互作用し、様々な有機・無機化合物から電子を引き抜いてエネルギーを得ているのである。このような多様な微生物機能によって、微生物は、自身がおかれた環境の地球化学エネルギーを積極的に利用している。
「研究目標3」では、シトクロムcおよびその他の電子伝達蛋白質の機能である電子伝達反応を測定し、その反応機構を立体構造情報とあわせて明らかにする。また、シトクロムcなどの電子伝達蛋白質に一分子操作技術を適用し、生体分子機能を組み合わせたエネルギー変換装置を創出するなど、生物機能を利用した新しいエネルギー生産技術を確立する。