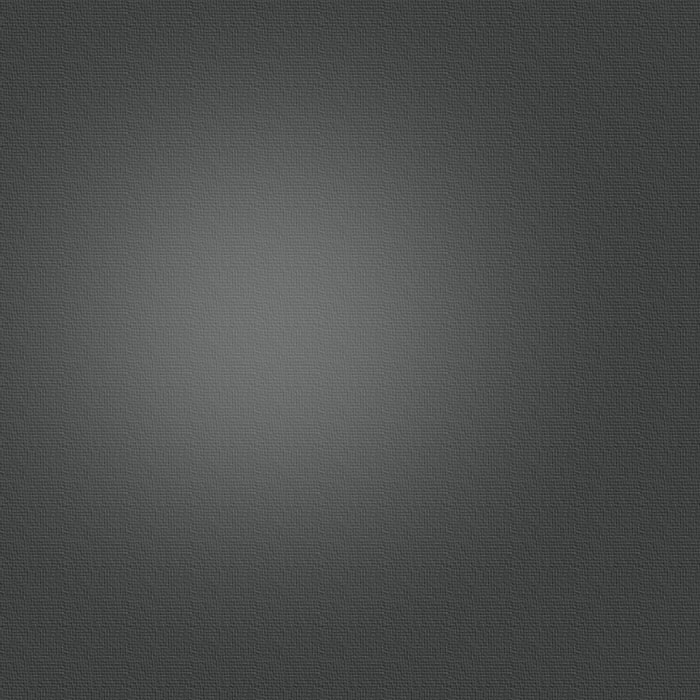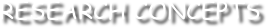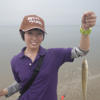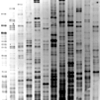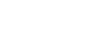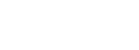遺伝資源の保全と遺伝的多様性 〜水産物は多様性の宝庫〜
生物の遺伝的多様性が低下してしまうと自然環境への適応能力が低下してしまい,種の繁殖はおろか,最悪の場合,絶滅しまうこともあります。このような事態をさけるために,2010年,生物多様性条約(1993年発効)の締結国が名古屋に集い,第10回締約国会議(COP10)が開催されたことは記憶に新しいと思います。生態系としての生物の多様性,生態系の種の多様性,個体群の遺伝的多様性を保全することで,最終的に人類が生物資源を永続的に利用し,遺伝資源の利用から生ずる利益を人類へ分配するのが目的です。
一方,水圏生物の大きな特徴は遺伝的多様性にあります。水産物は養殖魚をの除けば多くが天然だからです。イワシやサンマなどの多獲性魚類をはじめ,日本人の大好なイカやタコ類,広島名物のマガキがその代表例で,豊富な個体群の任意交配によって高い遺伝的多様性が保たれているのです。ですから,遺伝的多様性に富む水圏生物を保全することで,その半永久的な繁殖と食資源としての利用を目指すことが四方を海に囲まれた日本の責務なのです。
種苗放流と遺伝資源 〜責任ある放流に向けて〜
水圏生物を健全に保全するため,生物が棲息しやすい環境を提供することは大切です。ところが,私たちは少なからず埋め立てやダム建設などによって環境を破壊しています。そうした水産生物を捕り過ぎてしまうと,瞬く間に資源が枯渇してしまいます。致命的なのは個体の消滅によって遺伝子までも消滅しまうことです。一度,枯渇してしまった資源が量的な回復をしたとしても,遺伝的多様性の回復は不可能なのです。
「放流」,それは人の手によって育てられた放流魚を,直接,自然界に放流することで放流対象種への資源添加を目的とした行為です。乱獲によって減少した資源を回復させることや,資源を増やすことで水産生物の持続的な利用を目指しているのです。日本は世界に先駆け1960年代に海産魚の種苗の生産技術を確立し,放流事業でも毎年90種にもおよぶ海産水産生物を放流している放流先進国家です。
さて,ここまで放流事業と遺伝資源の保全の話を別々に進めてきましたが,実は両者には深い関わりがあるのです。放流種苗はごく少数の親魚から生産されたもので,自然界に比べ遺伝的多様性が低下した種苗が放流対象になることもあります。そうした種苗の多くが天然資源に加入すれば,対象種の遺伝的多様性までも低下してしまいます。放流魚同士,もしくは放流魚と天然魚が繁殖することで,負の影響が次世代まで浸透することもあるのです。一方,魚種によっては海域によって遺伝的に異なる集団を形成していることもあります。遺伝的に偏ったり,遺伝組成の異なる放流魚を放流してしまえば,本来の天然魚がもっていた集団構造が崩壊する危険性もあるのです。このような観点から,遺伝資源の保全までも視野に入れた責任ある放流が求められています。