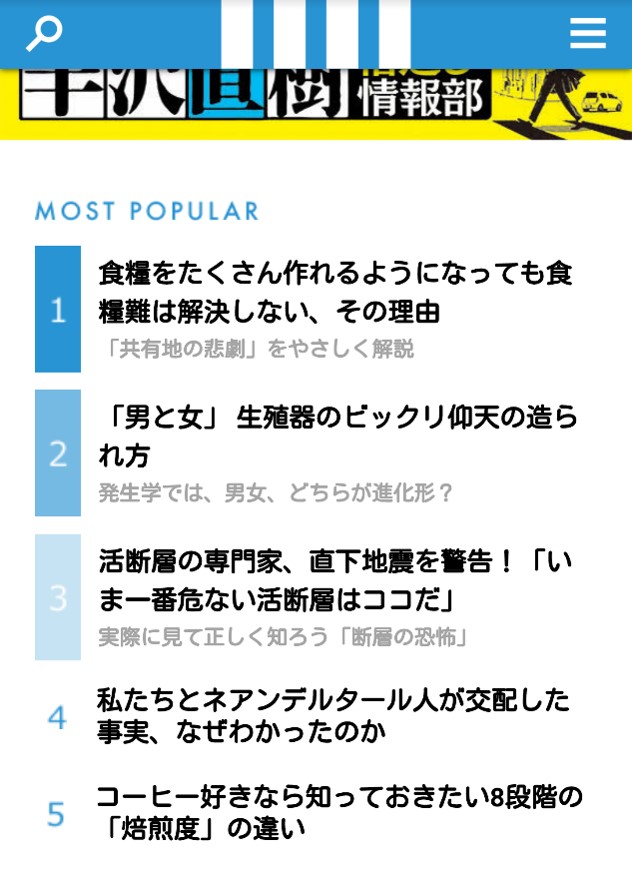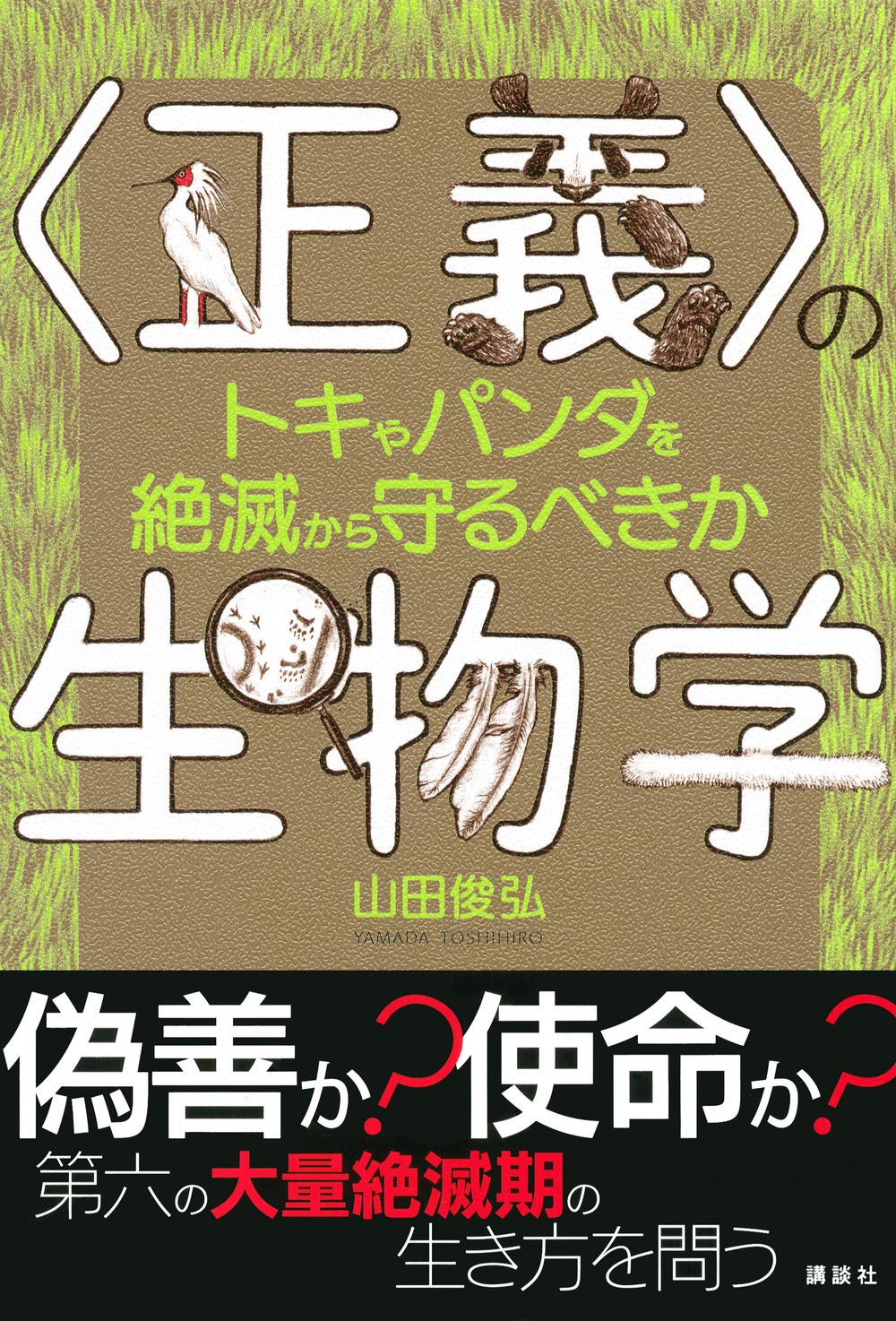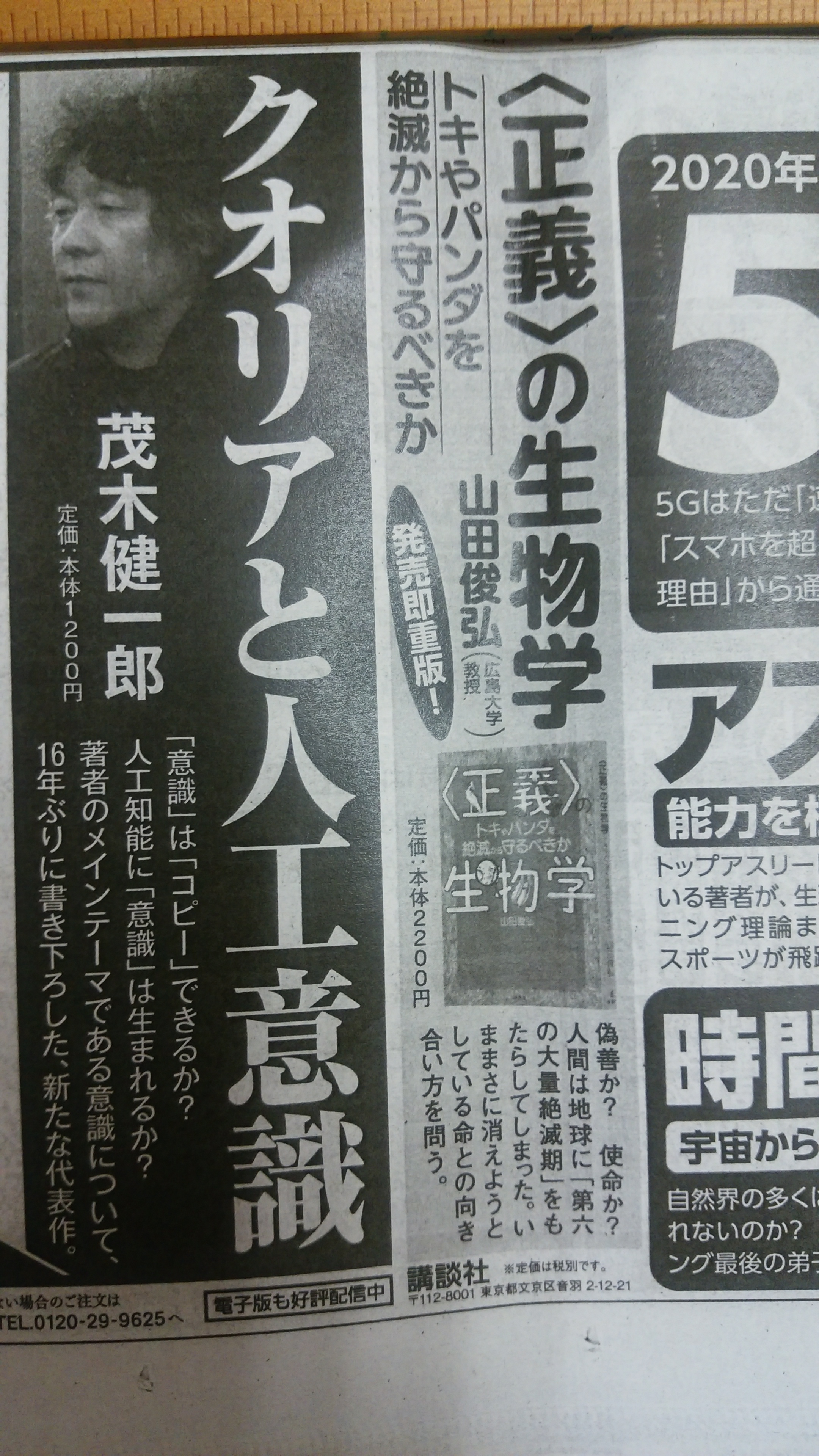私と部下は、さっきから双眼鏡をのぞいている。
といっても、双眼鏡をのぞくこと自体が目的ではない。双眼鏡で自然を観察しているのだ。生態学者っていうのはデフォルトで双眼鏡を首からかけて山の中を歩いておって、なんか珍しげなものを見つけると、片っ端から双眼鏡で観察する、という習性をもつ。
今回は私が、
「最高に開花しているブナの木がある!」
なぁんて言ってしまったので、開花の様をつぶさに観察しているのである。
というのはつい数分前の状況。双眼鏡をのぞいたら、開花中のブナの梢に鳥が止まって、盛んに花をついばんでいる様が見えちゃったもんだから、オブジェクトが秒で鳥に変わり、ついばむさまを愛でている、というのが現在の状況。
鳥は枝をかえながら、ブナの花をついばんでいるんだけど、どうも腑に落ちないのは花の感じがブナではない。幹直径が1mを超えるような大木だからブナかと思ったが、枝ぶりや花の感じから巨大なイヌシデのようだった。イヌシデは、こんなにも大きくなるのか!
ブナであってもイヌシデであっても風媒花だから、花粉媒介に鳥やら虫やらは必要ない。だから両種とも蜜を出さない花を付けるんだけれど、この鳥はイヌシデの花をさっきからずっと、すごい勢いでむさぼり食っている。だということは蜜ではなく花粉が目当てか。
鳥の食事風景に見入っていると、部下が双眼鏡をのぞいたまま、
「あれはアオバトです」
何て言うものだから、今見えているのは、もともとは青い色をしているハトだと勘違いした私は、
「見てごらんなさい。あのアオバトの体を。花粉で黄色く変色しておるぞ」
と、アオバトのことは昔からよく存じ上げていて、青い色をしたハトですよね。で、アオバトの地の青色が隠れちゃうぐらい体に黄色の花粉がついちゃってますねぇ、ということを、教授風口調で部下に、双眼鏡をのぞきながら感想を漏らしたのだが、それに対して部下が、
「いえ、あれがアオバトのもともとの色です」
なぁんて双眼鏡をのぞきながら言う。
全く腑に落ちない。今見ているのが地の色だったら、あいつらは本来、キイロバトかウスミドリバトと名付けられるべきである。そこで、
「アオバトなんだから、そんなわけないじゃん。花粉のせいだって」
と双眼鏡をのぞきながら反論すると、
「いいえ、いつものアオバトです」
と双眼鏡をのぞきながら言う。ここまで自信をもって言うんだから、きっと部下の言うほうが正しいのだろう。なんでこう昔の人っていうのは、訳の分かんない名前の付け方をするんだろうなぁ、おかげで辱めを受けたではないかと、と自分の知識不足を昔の人のネーミングセンスに転嫁しながら、やはり双眼鏡をのぞいていた。
そのうち部下が双眼鏡をのぞきながら、アオバトの鳴き声を知っているかと聞いてきたので、鳥研で我が研究室の卒業生の𠮷田が確か、
「アオバトは、あーお、あーお。と鳴く」
と言っていたのを思い出し、𠮷田の口調で、
「アオバトは、あーお、あーお、と鳴きますね」
と双眼鏡をのぞきながら言ったら、秒で否定された。
これには驚いたが、否定されるに思い当たる節もないわけではない。というのも、私はアオバトの鳴き声を知らない代わりに𠮷田がやったアオバトの鳴き声を知っていて、だからこそアオバトのまねをそのまましたのではなく、𠮷田がまねをしたアオバトのまねをしただけで、その伝言ゲームの中で、何か重要な情報が抜け落ちてしまったのであろう。
つまり、私は郷ひろみのものまねを得意ともしているのだけれども、正直に暴露すると私がやっているのは郷ひろみのものまねでもなんでもなく、郷ひろみのものまねをやっている人のものまねで、郷ひろみのものまねをしている人を知っている人はそれなりに感心しているのだけれど、郷ひろみのものまねをしている人の時点ですでに、郷ひろみがかなりデフォルメされているので、私がそれをまねる段階に至ってはもう、ほとんどそこに郷ひろみは残っておらず、郷ひろみのものまねをしている人を知らない人の場合は、私が郷ひろみであることが全くわからないのである。
そういった場合は空気を読んで、最後に、
「のぉー ひろみです」
と自己紹介を加えてその場をつくろうようにしている。
しかし、アオバトの場合は、「あーお、あーお」の後に、「アオバトです」、と自己紹介を加えたとしてもしっくりはまらないというか、さらに分かりにくさが増量されるだけなので、それさえもできない。まったく手の施しようのない状況の中、こうなったのもすべて𠮷田のせいだと謬見した私は、「𠮷田、ぶっ殺す」、と全く罪のない𠮷田への復讐を、黄色いアオバトを双眼鏡で凝視しながら心に誓った。
すると、である。部下が、
「アオバトは、尺八の音色です」
と、双眼鏡をのぞきながら正解を教えてくれた。この時点で私は、部下が何言っているのかわからなかったのだが、「ちょっと何言っているかわからない」、と思ったことをそのまま言うのはどうかとも思ったので、無視しておいた。
こういうときは双眼鏡は便利で、現在観察に夢中になっていて返事ができませんよぉ、という虚偽の振る舞いがしやすいのである。が、さっきまで郷ひろみ、じゃなくてアオバトのものまねをしていた私が急にだんまりを決めこんだので、かなりの違和感が残ってしまい、結果、部下はもう一度、
「アオバトは、尺八の音色です」
と双眼鏡をのぞきながら言い放った。
これは、「大事なことだから、2回言いました」、ではない。だって、「アオバトは、尺八の音色です」は、たぶん試験には出ないから。じゃあ、何で2回言ったかというと、たぶん、「なんか言え」という気持ちが託されているのだと思う。しからばこれは大変な状況で、だって私は何か言わないといけないから。
もしかすると諸君はここで、こんなもの大変な状況でも何でもない。大袈裟だなぁ。さっさと何か言えば済むことではないか。もしかすると阿保。あほなのだろうか、と思われたかもしれないが、阿保に対しては漢字で阿保を表記するよりもむしろ平仮名の方が相応しい、という気まで使っていただいて大変恐縮ではあるのだが、阿保ではない。それでは、この状況が如何にして大変な状況にまで発展するのかを解説することにしよう。
もちろん私にも、言葉に託された気持ちは十分に伝わりましたよ。だから、何か答えようとも思った。これは嘘、偽りのない気持ち。でもね、思ったんだけど残念、なにも言えないの。
なぜならば、私は尺八にも造詣はあっさーく、尺八の音に対して漠や然としたイメージならば持っているが、それ以上のイメージを持ち合わせておらない。だから、「アオバトは、尺八の音色です」に対してなんら、具体的な話を膨らませられないのである。仕方がないので、力なく、
「ははははは」
と何に対しての笑いかわからない笑いで返したのだが、笑いながら、「笑ってごまかすとは昔の人はうまく言ったものだな」、と感心した。
すると、部下は、ごまかされていることを見透かし、双眼鏡をのぞきながら何らかの奇妙な音を発した。
たぶん、アオバトの鳴き声かと思うけど、もしかするとワンチャン、一般的な尺八の演奏を再現されたのかもしれない。
まぁ、たぶん、この場合で後者を採用するのはかなりの変化球投手なので、きっと前者だろう。
不思議な音色だった。これが、アオバトか。そして、これが尺八に似ておるのか、と双眼鏡をのぞきながら感心した。そして、全然𠮷田っぽくなかった。
で、山から下り、研究室でユーチューブにあるアオバトの鳴き声を聞いたんだけど、部下の出した音の通りだったので、もう一度感心した。
あーお あーお

ブナの開花