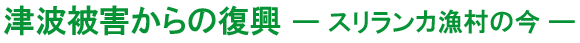|
1 |
新しい漁村社会の成り立ちとは? |
|
|
居住空間としての漁村、生産の場としての漁村のかなりの部分が破壊されてしまいました。海辺から遠く離れた場所に移り住んでいる漁業者が相当数います。これまであった漁村内の人間関係、取引関係、生産をめぐる諸関係が崩壊したところも多いようです。
漁業に携わる人々は、転居した先で、漁業のための社会的、経済的、文化的な基盤をどう再建してゆくのでしょうか。それは、津波以前にあった漁業生産と生活の単位としての漁村と同じ社会になるのだろうか、という疑問がわいてきます。
|
|
|
|
|
2 |
漁港・水産インフラの整備のあり方 |
|
|
現在、スリランカの主要漁港のほとんどが復興工事中か、近々復興工事にとりかかかることになっています。復興工事は、今後の水産施策のあり方と関連させて進められることが望まれます。 |
|
|
|
|
3 |
漁民・漁村支援と資源管理とのバランス |
|
|
支援活動の充実にともなって、性能のいい小型漁船が急増し、以前にくらべて漁獲努力量が増えています。過剰漁獲を心配する声があがり、減船政策(Buy-back program) の導入が必要だと主張する政府・援助関係者も少なくありません。 |
|
|
|
|
4 |
漁村社会における格差拡大の懸念 |
|
|
被災漁民に対して、漁船・エンジン・漁網の支給が順調にいっているわけではあり ません。補償をめぐって汚職が広がり、被害の実態を反映しない支給が横行しているという声を耳にしました。本当のところはわかりませんが、私たちが訪れた仮設住宅の状況、漁船所有をみて、格差が広がっているのは間違いないようです。
|
|
|
|
|
5 |
協力・共同活動の動き |
|
|
一方、住民が協力・共同する動きも盛んです。NGO が支援していることもあって、マイクロファイナンスの組織化、共同購入や共同販売の試みが各地で実施されています。これらの活動を、今後どのように持続させていくかが課題になっています。
|
|
|
|
|
6 |
地方自治体の再建 |
|
|
被災地の地方自治体の再建が大切な課題になっています。多数の自治体関係者が亡くなり、施設も破壊されてしまったので、復旧活動では地方自治体が十分な役割を果たせませんでした。それに、役人の汚職が蔓延して、住民の信頼を失ってしまった地域が珍しくありません。世界各地から押し寄せてきたNGOの活動は、結果的に、住民の自治体への参加・結集を妨げてしまいました。自治体を再建していくことは容易なことではありません。 |