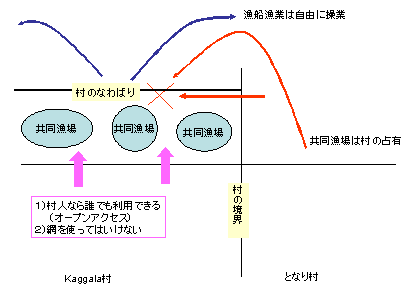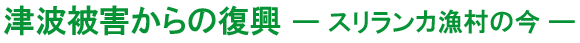
| 7.カゴラ村(Kagalla)【ハンバントタ郡(Hanbamtota郡)】 | |||
1) カゴラ村の釣り漁業 |
|||
| ここには有名な釣り漁業(英語ではspot fishing)があります。スリランカのガイドブック、絵はがきには必ず登場してくる漁村の光景です。 | |||
 |
 |
||
|
写真62・63 釣りの様子
|
|||
| ハンバントタ郡にあるこの村には、三つの漁場があります。この漁場は村が管理する”共同漁場”で、村民なら誰でもが利用できます。棒はどこに打ってもかまいませんし、他の人のものもあいていれば使用してよいのです。1人が3本くらいのサオをもって棒にのぼって、小魚(イワシ・アジ類の魚)をひっかけます。 | |||
 写真64:商人が買い付けているところ |
 写真65:小さな販売所 |
||
釣れた魚は、その場にまっている商人に販売されます。魚種別に尾数を数えて精算される。海に入って釣る時間は、平均すると3−4時間くらい。販売金額に幅がありますが、私たちが訪れた際には、1人あたり500ー600ルピーでした。 この漁は、小型漁船では漁ができないモンスーンの時期におこなわれます。漁家の収入がもっとも少なくなる時期なので、貴重な現金収入になっています。ただ、風と波に直接さらされるこの漁は、みためほど楽なものではありません。3−4時間の漁を終えてあがってきた男たち唇は真っ青で、誰もが体を震わせていました。 |
|||
|
|||
 写真66:防波堤ができる前は砂浜だった |
このような防波堤がもうひとつあれば、というのが村人の要望です。釣りがしやすくなり、小型船を係留できます。多少の波があっても漁にでられます。 | ||
2) デワタ(Dewata)村の地曳き網 |
|||
| ここには、メデル(Me-del)と呼ばれる大型の地曳き網が2統あります。2人の網元が1日ごとに交代で網をひきます。網を積んだ船には7人が乗船しますが、浜では50-70人もの人が網をひきます。 | |||
 写真67:漁を終えて船を浜にひきあげる |
|||
村住民であれば誰でも地曳き網漁に参加できます。網元は参加人数を限ることはしていないようです。多い日で3回網をいれることがあります。参加する住民は1日に500-600ルピーの収入をえることができ、貴重な就業先・収入源になっています。 |
|||
 写真68:対象魚種はいわし、アジなど |
 写真69:網のかたづけ |
||
漁獲対象魚種はアジ、イワシなどの小魚が中心です。網の長さは2kmにも及びます。網元が漁獲物の何割をとるかは聞けませんでしたが、その配分方法は、漁村住民の相互扶助、「貧困の共有」的な性格をもっています。カゴラ村の釣り漁場の共同利用と似ているのかもしれません。 |
|||