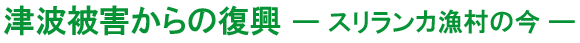
| 5.ティッサマハーラーマ(Tissamaharama) 【ハンバントタ郡(Hanbamtota郡)】 | ||
1) キリンダ漁港(Kirinda Fishery Habour) |
||
| 東部に位置するキリンダ漁港は,日本の政府開発援助によって20年位前に建設されました。砂の堆積がひどく,港が使いにくい状況にあったため,支援工事が追加で行われてきました。砂丘地形が広がるこの地域の自然条件は、農業生産には適していません。沿岸住民の多くが漁業に依存して生計をたてています。使い勝手のよい港ではありませんが、漁業で生計をたてる漁民にとっては、必要不可欠なインフラです。マグロ・カツオ漁を営む"Multi-day boat"が集まる拠点港として栄え、漁獲漁業を中心になりたつ地域経済を支えてきました。それが、堆積する砂で使えなくなり始めたのは、4−5年前からと言われます。 | ||
 写真42:キリンダ漁港 |
||
 写真43:船外機付き漁船が係留されている |
オークション・ホールの前には小型漁船が係留されている点が、これまで見てきた漁港と大きく違う点です。Multi-day boatの姿が港内に見あたりません。決して、カツオ・マグロ類を対象魚種とする中型漁船がこの地域にない、ということではありません。他港にあるか、沖に泊めてあるのです。 | |
 写真44:津波被害を受けた浚渫船(係留して修理中) |
港では津波で壊れた浚渫船を係留して修理中でしたが、この船をえい航してくるために港内を閉めきって海水を入れる必要があったようです。それほど、砂の堆積がひどいということです。小型船は出入り口をふさがれることになり、港の出入りには砂の上を押していくことになります。不便を強いられています。 |
|

|
 写真46:砂で閉じられた港 |
|
 写真47:港の外側におかれた小型船 |
港の外側には多数の小型船がとめられています。港内に入る不便さをきらって外にとめる人が多いと聞きました。波が荒い日には砂浜でエンジンをかけるのは大変で、2人の作業員を雇って船を押さえておくそうです。なんとかならないものか、と漁民がぼやいておりました。 | |
| 津波被害は相当に大きなものでした。事務所は完全に破壊され、オークションホールは屋根が流されたと言います。ワークシップは枠組が残っただけでした。製氷施設はまったく使いものにならず、漁業者は困っていました。4か月ほど前、日本政府からコンテナ型製氷機・貯氷機が送られてきましたが、まだ稼働はしていないようです。氷は大切な資材ですので、早い復興が望まれます。 | ||
 写真48:枠組が残ったワークショップ |

|
|
 写真50:ロブスター用の網を広げる漁民 (港外の砂浜にて) |
 写真51:砂に囲まれた港 |
|
| 港内および周辺ではMulti-day boatの姿をみることはありませんでしたが、網を修繕する漁民がいました。ここでも、沖合漁業は地域住民に雇用の場を提供しています。4−5年前には150隻近くあった漁船(Multi-day boat)は、今では50隻にまで減っています。1日もはやい復興がまたれるところです。 | ||
 |
写真52:網を修理する漁民 |
|
2) 被災者のための仮設住宅:漁港周辺のキャンプ |
||
| キリンダ港周辺には今も仮設住宅で暮らす人がたくさんいます。家と漁船・漁具を失ったパティさん一家は、被災後3−4か月で小型漁船(15HPの船外機付き)の寄贈を受けて漁の再開にこぎつけました。被災はしたが、運がいいほうだとのこと。しかし、キャンプ地の住環境は劣悪で、当初はテント生活で不自由したといいます。今は仮設に住んでいます。 | ||
 写真53:仮設住宅の様子 |
 写真54:パティさん一家と (ご主人は網の修理作業で外出中) |
|
 写真55:仮設住宅地 |
この仮設住宅には20軒が入居しましたが、現在は、12軒に減っています。NGOが近くに家をたててくれていますが、資金の半分を負担しなければならないため、建築は止まったままです。 | |
 写真56:ココヤシ繊維の縄作り |
 写真57:縄で作ったほうき |
|
| どのキャンプもそうですが、住民はさまざまな内職に励んでいます。これは一例で、ココヤシの繊維を使った縄作りがNGOによって紹介されています。ここに住む人たちが仮設をでていくまで、まだまだ時間がかかりそうです。 | ||