幼児期の発達を探求する 杉村研究室
発達の謎に挑もう,発達の本質に迫ろう,発達の仕組みを解明しよう。
研究室の紹介
杉村研究室は, 広島大学 大学院人間社会科学研究科 附属幼年教育研究施設(幼研) の中にあり,幼児期の発達を探求しています。具体的には,以下のテーマに取り組んでいます。アファンタジア
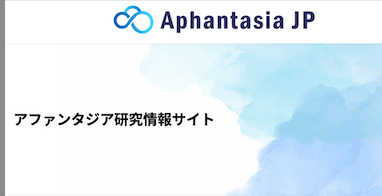 あなたは人の顔やリンゴなどを思い浮かべることができますか? 最近の研究により,数%の人が,実際に目の前にある物や人の知覚は機能しているが,心的イメージの形成が難しい特質をもっていることが明らかになってきました。そのような特質もしくは特質をもつ人をアファンタジアと呼んでいますが,私もアファンタジアの一人です。
あなたは人の顔やリンゴなどを思い浮かべることができますか? 最近の研究により,数%の人が,実際に目の前にある物や人の知覚は機能しているが,心的イメージの形成が難しい特質をもっていることが明らかになってきました。そのような特質もしくは特質をもつ人をアファンタジアと呼んでいますが,私もアファンタジアの一人です。イメージのない世界で生きるアファンタジアの理解と支援につながる研究を行っていきます。 詳細⇒
数の理解
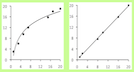 4個のおはじきと3個のおはじきを手で合わせることと,4+3=7という足し算との間に関心があります。「具体的なものを操作する」ことと「言葉や記号を操作する」ことが,子どもの頭の中でどのようにつながっていくのでしょうか。この謎に挑戦するために,ピアジェの理論に加えて近年注目を集めている身体性認知科学の知見を援用し,行為や活動を通した数の理解のプロセスを検討しています。
4個のおはじきと3個のおはじきを手で合わせることと,4+3=7という足し算との間に関心があります。「具体的なものを操作する」ことと「言葉や記号を操作する」ことが,子どもの頭の中でどのようにつながっていくのでしょうか。この謎に挑戦するために,ピアジェの理論に加えて近年注目を集めている身体性認知科学の知見を援用し,行為や活動を通した数の理解のプロセスを検討しています。具体的には,計算時の指の利用を調べてきました。また,手指の巧緻性と計算能力の関係を検討することにより,運動発達と認知発達との関連を明らかにしてきました。最近は,心的数直線の形成過程や児童期の学力への影響を検討したり、数への自発的焦点化(SFON)の尺度作成を行なったりしています。 詳細⇒
子ども理解
 保育者の実践と成長において省察は重要な役割を果たすと考えられています。しかし現在のところ,保育における省察に関する基礎研究は少なく,省察の際に,どのような知識が利用され,どのような認知活動が行われているのかが体系的に記述・説明されていません。したがって,保育者が何をどのように省察すればよいのかが明確でなく,省察による実践力の向上や実りある保育カンファレンスの実現を難しくしています。そこで私たちは,メンタルモデルや原因帰属といった観点から,省察に関する知識の構造や省察の機能を検討しています。
詳細⇒
保育者の実践と成長において省察は重要な役割を果たすと考えられています。しかし現在のところ,保育における省察に関する基礎研究は少なく,省察の際に,どのような知識が利用され,どのような認知活動が行われているのかが体系的に記述・説明されていません。したがって,保育者が何をどのように省察すればよいのかが明確でなく,省察による実践力の向上や実りある保育カンファレンスの実現を難しくしています。そこで私たちは,メンタルモデルや原因帰属といった観点から,省察に関する知識の構造や省察の機能を検討しています。
詳細⇒遊びのリスク・ベネフィットバランス
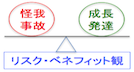 保育現場では,怪我や事故を減らすためにリスクマネジメントが行われるようになりました。一方で,過度な安全性の追求はかえって健全な発達を阻害する,と考えられつつあります。しかし,実証研究はほとんどありません。そこで私たちは,保育における遊びのリスクとベネフィットの問題を,保護者・保育者・子どもの,三者内ならびに三者間における動的なバランスの調整過程として総合的に捉え,検討しています。また,子ども自身によるリスクマネジメントを自己調整学習の枠組みを援用して検討しています。
詳細⇒
保育現場では,怪我や事故を減らすためにリスクマネジメントが行われるようになりました。一方で,過度な安全性の追求はかえって健全な発達を阻害する,と考えられつつあります。しかし,実証研究はほとんどありません。そこで私たちは,保育における遊びのリスクとベネフィットの問題を,保護者・保育者・子どもの,三者内ならびに三者間における動的なバランスの調整過程として総合的に捉え,検討しています。また,子ども自身によるリスクマネジメントを自己調整学習の枠組みを援用して検討しています。
詳細⇒