|
フィリピンの漁業協同組合と漁村振興
ーパラワン島北部の事例ー |
| 4.カラマイ生産者協同組合の組織と事業 | ||||
1)バランガイ・カラマイの様子 |
||||
カラマイ村(バランガイ)は、ロハス(Roxas)町にあります。プエルト・プリンセサから車で1時間半、パラワン島の東側に位置しています。37のバランガイがありますが、うち海岸に面しているのは17のバランガイです。 |
||||
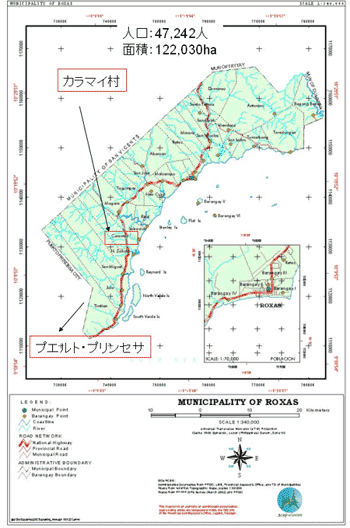 図4 カラマイ村(ロハス町)の地図 |
||||
 写真12:静かなたたずまいの漁村風景 |
 写真13:庭があり花があふれている家が多いのが印象的 |
|||
| 落ち着いた漁村風景がとても印象的です。漁村の人口密度が高くないからでしょうか。広い道路、広い庭、それほど立派な家ではありませんが、豊かに見えました。 | ||||
2)釣り、刺し網、まき網が主な漁業 |
||||
零細漁業が中心で、釣り、刺し網、それに小さなまき網類が主な漁具です。対象魚種は、ハタ、タイ類、サワラ、バラクーダ、サプ・サプ、バリア(handtail)、カニ、エビなど、実に豊富です。満干潮の差が3mくらい。浜からかなり離れた浅瀬でも採貝が行われます。干潮時には水揚げするのが大変なようです。 |
 写真14:この村では大きい部類の漁船 |
|||
 写真15:エコ・ツーリズムのための簡単な桟橋(満潮時) |
 写真16:干潮時の桟橋の様子 |
|||
 写真17:このサイズの漁船が多い(無動力船、釣りなど) |
 写真18:干潮時の沖合の様子 |
|||
3)組合発足の経緯 |
||||
| カラマイ生産者協同組合(以下、カラマイ漁協と呼ぶ)の正式名称は、"Association of Small Fishermen of Caramay Producers Cooperative"です。Association(協会)と Cooperative(組合)の名が二つもっているのが、なんとも不思議です。この名前の由来は、協会として発足したという経緯からきています。NGOの支援を受けて、協会として設立されたのが1998年。組合(cooperative)に組織替えしたのが2001年です。 | ||||
 写真19:組合の事務所(エコ・ツアーの宣伝ポスターなど) |
||||
 |
写真20:優良組合として県知事から賞をもらった |
|||
4)バランガイを基盤にした組合活動(”Barangay-based Cooperative”) |
||||
現在の組合員数は62人。男性が8割、女性が2割です。村の総世帯数が500戸ですから、必ずしも組織率の高い組合ではありません。組合員はバランガイの住民。この組合の特徴は、バランガイを基盤に活動していることです。私たちは、こうした組合を、”Barangay-based Cooperative”と呼んでいます。
組合がおこなっている事業活動は次の4つです。 1)魚類養殖 2)ナマコ養殖 3)エコ・ツーリズム 4)資源管理活動 |
||||
5)魚類養殖とナマコ養殖 |
||||
| バランガイの浜から少し離れたとこに、浅瀬があって小さな島のようになっています。その周辺で、魚類養殖とナマコ養殖が行われています。魚類養殖が始まったのは3年前。日本の漁協ふうにいえば、「組合自営」です。外から養殖業振興のための支援があって、組合員が共同で始めたものです。 | ||||
 写真21:枠組のしっかりした魚類養殖の筏。ドラム缶 を使って組んでおり、小屋には管理人がいる。 |
||||
 |
写真22:作業がしやすい生け簀。 ハタ、ゴルビーなどを養殖。 |
|||
ハタ養殖の損益分岐点は、kg当たり200ー250ペソ(Green grouperの場合)。赤字はでていないとのこと。エサは生エサです。写真のように、電灯を集魚灯にしておけば、小魚が簡単にとれるといいます。それでは足りませんから、刺し網でとった小魚をエサにします。 |
||||
 写真23:エサとなる小魚を集める”集魚灯”。 網を引きあげれば生エサがえられる。 |
 写真24:組合のレストランで調理中のハタ。 1.2-3kgはあった。 |
|||
成長したハタ(現地でGreen grouperとRed grouperと呼ばれる2種類が養殖)は市場で販売。組合が運営しているレストランでも提供しています。 昨年から組合が始めたのが、ナマコ養殖です。輸出向けナマコ生産がブームですが、昨年は台風で収穫がまったくなかったとのこと。今年、再挑戦で4か月目にはいったそうです。1haの養殖場には4万個のナマコを放流。収穫したナマコは乾燥させますが、1kgの干しナマコをつくるのに10個が必要とか。干しナマコのkg当たり価格は3800ペソです。 |
||||
 写真25:組合のナマコ養殖場、1haの広さ。 近くには民間業者の養殖場も。 |
||||
 写真26:とれたナマコ。これを乾燥させて 販売するとkgあたり3800ペソにもなる。 |
組合自営で行う魚類・ナマコ養殖の事業活動については、今後くわしい聞きとり調査をするつもりです。 | |||
6)エコ・ツーリズムへの取組 |
||||
| 組合が力を入れているのがエコ・ツーリズムです。バランガイの浜のちょっと沖に、砂浜が盛り上がったところがあり、そこにレストランをたてています。その横には、魚養殖の生け簀、コテージも浮いています。エコ・ツーリズムの拠点です。 | ||||
 写真27:”Purgtod Sand Bar"と呼ばれる小さな島。 組合がレストランをたてている。浜の桟橋から15分。 |
||||
| もちろん魚介類中心の料理を提供。エビ、カニ、ハタ、タイ、貝、海藻などがお皿に一杯。果物は、ありふれてますが、"local variety"のバナナ(味が濃い)、マンゴなど。養殖生け簀からとってきたばかりのハタがグリルにされます。 |
 写真28:大人数にも対応できる |
|||
 写真29:海産エビがもつうま味・あま味は最高! |
 写真30:「海に浮かぶコテージ」を準備中。 |
|||
バランガイには海のサンクチュアリ(保護区)があったり、マングローブがあったりと、自然が豊かです。これらを利用したツーリズムを楽しむことができます。 |
||||
7)沿岸資源管理への取組 |
||||
| 組合事業のなかで、大きなウエートを占めるのが沿岸資源管理に関する事業です。バランガイ前の海域には、50haのサンクチュアリが広がります。"Community-based Marine Sanctuary Management and Livelihood Support Project"という、UNDP(国連開発計画)支援のプロジェクトとして始まったもので、マニシパル条令にもとづいて、サンクチュアリが管理されています。 | ||||
 写真31:サンクチュアリを示すブイ。侵入禁止を よびかけている。白いフロートはロープ。 |
 写真32:養殖生け簀にある小屋。ここはサンクチュアリ 周辺の違法操業を監視する役割も果たしている。 ("Monitoring Station"と書いてある) |
|||
 写真33:レストランにあったプロジェクトのポスター。 組合自営の養殖業もプロジェクトの活動のひとつ。 |
特徴的なことは、サンクチュアリの監視が、バランガイ内の住民組織である組合の活動のひとつだ、ということです。普通、"Bantay Dagat"と呼ばれる監視組織が、バランガイにはありますが、カラマイ村では、組合がその役割の一端をになっています。漁民にしてみれば、村の中で行われる活動であれば、Bantay Dagatと組合を区別する必要がないのかもしれません。養殖生け簀の小屋で監視がおこなわれます。 |
|||
|
図5 カラマイ村の"Community-Based Marine Sanctuary"と関連事業 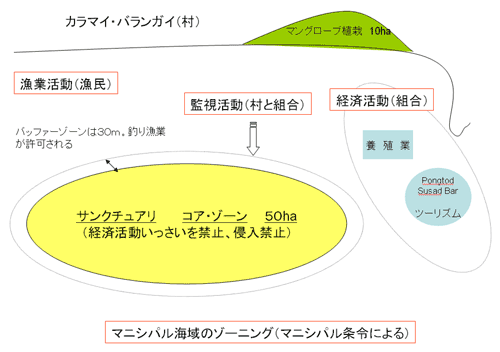 |
||||
| サンクチュアリの取り囲んだ周辺30mが、バッファ・ゾーンです。ここでは、漁業活動が許されますが、釣り漁業だけです。サンクチュアリを設定する際、漁民の中には強く反対する動きがありましたが、その外側での漁獲量が増えたため、今では反対する人はいないとのことです。 | ||||