|
フィリピンの漁業協同組合と漁村振興
ーパラワン島北部の事例ー |
| 5.マニシパル政府と漁業協同組合:San Vicenteの試み | |||||||||||||||||||||||||
1)サンビセエンテ町の様子 |
|||||||||||||||||||||||||
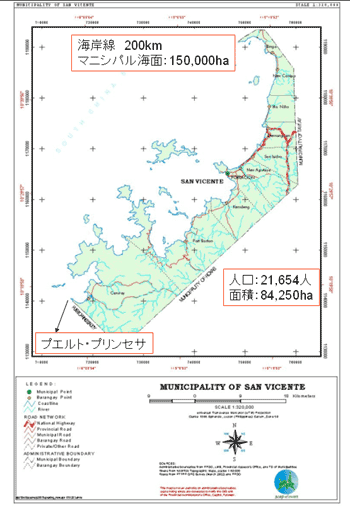 図6 サンビセンテ町の地図 |
|||||||||||||||||||||||||
サンビセンテは、パラワン北部の西海岸に位置する、広大な面積をもつ町(マニシパル)です。人口は約2万1千人、陸地面積は8万4千ヘクタール、人口成長率が2.33%。他からの流入してくる人口が多いのでしょうか。いわゆる、"Munichipal waters"(町が管轄する海域)は15万ha、海岸線は地形が入り組んでいることもあって、200kmにも達します。 この広大な海域を、町はどのように管理しているのでしょうか。今回は、漁業・漁村の様子よりも、行政組織としてしての資源管理組織に重点をおいて、聞きとりをしてみました。 |
|||||||||||||||||||||||||
 写真34:サンビシエンテ町の庁舎 |
 写真35:行政担当者、漁協組合員らとの意見交換の様子 (サンビセエンテ町の会議室にて)。 |
||||||||||||||||||||||||
2)バランガイ組織の集合体:漁協 |
|||||||||||||||||||||||||
|
漁協の名前は、"Bagong Siglo Ng Mga Mangingisda Multu-purpose Cooperative"(New Century Fishermen Multi-purpose Cooperative)です。2002年10月に設立が認可されました。発足時の組合員数は51名。10のバランガイ(村)から5人ずつ参加、残り1名は、監視組織である"Bantay Dagat"の代表者です。この組合は、バランガイ組織の連合体になっているのが特徴的です。出資金は1口40ペソ、32,649ペソが当初の予定出資金です。 |
|||||||||||||||||||||||||
3)漁業条令のなかの漁協 |
|||||||||||||||||||||||||
| マニシパル海域の管理は、"Municipal Fishery Regulatory Board (MFRB)"が中心になって行うことになっています。MFRBでの検討を経て、議会(Sangguniang Bayan)が条令を作ります。その過程で重要な役割を果たすことになっています。 | |||||||||||||||||||||||||
|
図7 サン・ビセンテの資源管理組織:漁協の位置 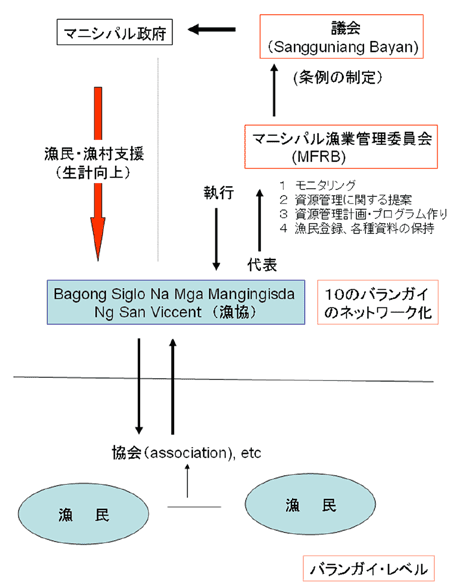 |
|||||||||||||||||||||||||
村のレベルでは、漁民が参加する協会(association)が組織されます。協会は、資源管理に関する事柄をあつかっていることから、BFARMC(Barangay Fishery & Aquatic Resource Management Council, バランガイ資源管理委員会)の役割を果たしているようです。漁協は、10の村の協会が集まったものです。マニシパル漁業管理委員会には、漁協が漁民代表として参加します。 委員会は、1)モニタリング、2)資源管理に関する提案(議会)、3)資源管理計画・プログラム作り、4)漁民登録、各種資料の保持、など総合的な機能をもっています。漁民組織、Banday Dagat、関係政府機関が集まって、資源管理計画を作っていますので、マニシパル政府の役割の相当部分が、この委員会に委ねられている、と言えます。 |
|||||||||||||||||||||||||
4)漁協の役割はなにか?:資源管理と経済事業(Livelihood project)の結合 |
|||||||||||||||||||||||||
|
漁協には次のような2つの顔があります。
漁協は、漁民の生計向上をはかりながら、持続的な資源利用のための諸方策を実現しようという狙いをもって設立されたものです。 サンビセエンテのように、管轄する海域が広い場合、バランガイを単位に資源管理をおこなう必要があります。そのうえで、マニシパルのレベルで統一した資源管理を実施することになります。MFRBは、「ネットワーカー」としての役割、マニシパル政府とバランガイとの間にあって、両者の間をとりもつ、中間的な位置にあります。 |
|||||||||||||||||||||||||