| I バンダ・アチェから |
1 復興途上にある漁村 |
2004年12月のスマトラ沖地震・津波発生以来,被災住民および地域社会は,インドネシア政府,国際援助機関,国内外のNGOの支援を受けて復興に努めている。東南アジアの他の被災国に比べて,その被害状況が桁はずれに大きい。地震に加えて津波の直撃を受けたバンダアチェでは復興が進んでいるとはいえ,今もなお津波被害の傷跡がなまなましく残っている。

写真1:新しい漁村のたたずまい(Banjir Kanal Krung Ache周辺):真新しい住宅と漁船
被災した住民の気持ちも少し落ち着いたと言われる。私たちの聞きとりは,復興過程のこと,漁業を中心とした生計のたてかた,資源利用のあり方を中心にしたものだったが,自身や家族のことに話題がおよぶと,瞳がたちつくし,空をながめて涙をながす漁村住民にも出会った。復興の進捗状況と人々の心情との落差を目の当たりにするにつれ,聞きとり調査をすることの難しさを思い知らされた。
写真2:破壊された道路。漁村集落のあとかたもない(Desa RitungからDesa Meunah Baka Laupungに行く途中)。道路は建設されているが未舗装が多く,遠くの漁村に行くにはかなりの時間がかかる。道路整備の遅れが遠隔地の漁村の復興をいっそう困難にさせている。
写真3:漁船のない漁村。インド洋側には荒涼とした光景が広がる。多くの死者をだしたこの村では漁業の担い手がいなくなった。カタクチイワシの棒受け網が盛んだった。
復興は地域間の不均衡な発展を内包させながら進められている。バンダ・アチェを中心に復興が始まり,そこから距離が離れるにしたがって立ち遅れが目につく。西より東,マラッカ海峡よりインド洋に面した漁村の悲惨さが目にやきついている。
|
2 新しい段階に入った復興プログラム |
インドネシアで復興を中心的に担っているのが"Rehabilitation and Reconstruction Agency"(Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BRR)である。インドネシア政府においては復興計画・事業の調整の役割を果たし,国連とその諸機関と協力し,世界の援助国と連携をとりながら,現地に入ってくる無数のNGOに対して被害および復興情報を提供している。現在,復興計画は,緊急支援を中心とした第1段階をへて,第2段階に入っている。漁業についてみると,漁船の建造,漁具の購入,漁村インフラの再建に加えて,それを支える販売や融資ネットワークの整備が重視されている。この段階を経て,被災地域及び住民が自立していくことが求められている。復興支援は,ハード分野の支援からソフト分野に重点を移している。
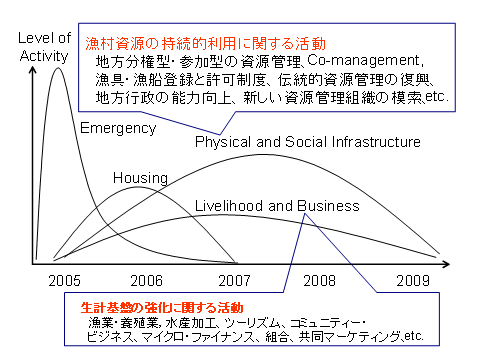
(資料)BRR 2005. Ache and Nians One Year After the Tsunami: The Recovery Effort and Way Foward, p.19.
図1 復興の5か年計画とプログラム
|
3 漁業インフラの復興状況
|
復興は順調かと問うと,実にさまざまな答えが返ってくる。私たちがバンダ・アチェ周辺の狭い範囲で見聞したかぎりでも,応対してくれた人々からの印象,地域の復興状況などから判断して,今この段階にあるととても結論づけることはできない。それほど,復興には大きな地域差があった。
漁業インフラの復興についてみると,バンダ・アチェ市内にある漁港はすでに補修が終わって機能していた。ロウプル漁港(Laupulu Port)では,水揚げする漁船や出漁の備に忙しい多数の漁船を目にすることができた。ここは,アチェ周辺から集まってくるまき網船団の基地にになっている。*
* まき網船だが船形はトロール船のように思えた。

写真4:"私たちBRRのプロジェクト":漁港入り口にて

写真5:まき網船の甲板

写真6:氷の積み込み作業

写真7:水産物小売り市場近くに係留される小型漁船 |
4 壊滅的打撃を受けた漁業と漁村:ウレレ地区 |
同じ,バンダ・アチェ市であってもインド洋に面して津波の直撃を受け,多数の被災者をだしたウレレ地区にある漁港は,現在も修復中であった。津波以前,この地区には3千人ほどの住民が住んでおり,そのほとんどが漁業世帯であった。しかし,現在の漁民数は45人くらいまで減った言われる。
仮設の水揚げ場があるが,利用できるのは船外機付きないしは船内機付きの小型漁船だけである。数隻の漁船が係留されていたが,これらは政府およびNGOの支援によって建造されたもの。この地区では多数の漁船が津波後に建造されたが,設計や技術に問題があって使えないものも少なくないという。エンジンも調子の悪いものが多いとのこと。漁民はむしろ船外機付き漁船を望んでいた。

写真8:ウレレ地区の漁港施設(現在も修復中)

写真9:仮設の水揚げ・取引所(ウレレ地区)。この施設は国連機関の援助で建てられた。

写真10:ウレレ地区の小さな水揚げ場にに係留されている漁船(政府からの支援で建造された)

写真11:供与されたが利用されないで沈んでいる小型漁船

写真12:漁港周辺には大きな漁村集落があった(コンクリート支柱が今も残る)
大きな漁村集落があったウレレは見る影もなく,インフラの復興もまだまだ軌道にのっているとはいえない。バンダ・アチェの市街地に近いこともあって,地域社会における漁業の存在感はすっかりあせてしまった。生き残った漁民の中には,海にでることの恐怖から,NGOが準備してくれた職業転換のためのスキーム(多くは回転資金計画,revolving funds)にのって,モーター・バイクを使ったベチャ(タクシーの一種)の運転手になるものもいた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|



