漁船建造施設とバガン漁業の操業
建造された施設は,プロジェクト終了後に建物と機材一式,各デサに贈与されることになっている。このプロジェクトは1年契約,2006年12月には活動を終えなければならない。かなり厳しい日程で作業が進められている。特に,バガン船に用いる9mの木材の調達が予想以上に難航して時間がかかり,作業が遅れぎみになっている。ただ,地域が一番欲しがっているバガン船を中心に復興を急いでいることで,それが及ぼす経済効果は大きく,地域住民の満足度は高い。バガン船を中心に復興計画を進めることで,
バガン漁業を営むために,プロジェクトでは漁具を提供し,バガン船を
貸付の形で現物供与している。建造できるのは24ユニット,津波以前には79ユニットあったが少なくとも30ユニットが破壊されたと言われる。建造できる漁船隻数が十分ではないため,「回転資金」制度を応用して,損害を受けた漁民に,公平に行き渡るようにしている。
また,プロジェクトではバガン漁業の操業を漁民が,操業資金の調達で困らないように,最初の6日間の操業費用を経営者に補填している。1日当たりの操業経費を,155,000ルピアと見積もり,最大で930,000ルピアを補助している。それ以降は,プロジェクトに頼らず操業を行うことになっている。なお,操業に先だって,GPS等を使って漁場・資源の分布状況を確認する訓練活動をプロジェクトで主催している。
漁業協同組合の設立と回転資金(revolving funds)
このプロジェクトを運営するにあたって,2006年2月に総合的な事業活動を行う協同組合(以下,組合)が設立された。この組合が対象とする事業分野は,漁業,金融(主に貸付),農業・畜産である。組合員は,プロジェクトに参加している3つのデサの住民である。
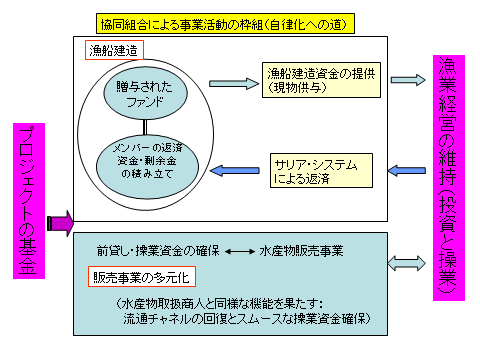
図2 協同組合方式による漁船建造事業と販売活動
漁船建造のための原資をプロジェクトが提供し,新たに設立された組合が受け皿となって,これを貸付原資として資金を回転させる。つまり,漁船はプロジェクトから組合に贈与されるもので,個人の漁民に与えられるものではない。組合から漁民に対しては貸付金として処理され,漁民は操業して得た利益のなかから一定額を返済する。組合は返済された資金を使って別の組合員のための漁船建造を行い,ふたたび貸し付ける。これを繰り返していくのが資金回転計画である。このシステムは,スマトラ島の生計復興計画のなかに広く取り入れられている。
クルング・ラヤ地区では,資金回転事業を他の事業運営と結びつけ実施するために,組合を設立した。これは,漁家経営の復興に総合的にかかわれるようにするためである。もちろん,こうした事業方式をとることについては賛否両論あったようで,組合を設立して復興活動を運営することには,プロジェクト側にも住民側にもためらいがあった*。しかし,最終的には住民側が組合を設立することを選択している。彼らが組合を選択した背景について,また,組合の事業活動の成果や問題点については,今後さらに検討する必要がある。
*これまでのインドネシアの漁村協同組合の経験から,「協同組合」には悲観的なイメージがあった。
集魚施設の設置と漁場管理
プロジェクトでは,クルング・ラヤ湾周辺に集魚施設(Fish Aggregating Devices, FDA)を2か所に設置している(当初は3か所であったが1基が消失)。生計プロジェクトのひとつとして設置されたもので,1基は湾奥から10km,もう1基は湾口の浜から沖5kmの場所におかれている。

写真25:湾口から5kmの位置にあるFAD。サンゴ礁に近くカタクチイワシがよく集まる。

写真26:湾奥から10km,ここではキハダやムロアジなどがつく。小型まき網漁船,棒受け網漁船の漁場になっている。
FADの設置場所については漁民自らが決めている。パングリマ・ラウト(集団)が3か月に1回,メインテナンスをおこなっている。地域外の漁船が入って周辺で操業することもあるが,利用料を徴収することになっている。
インドネシアはもとより東南アジアの海域では,海洋保護区(Marine Protected Area, MPA)をサンゴ礁などの保護を目的に設置する動きが盛んになっている。保護区の設置によって漁場の一部を失う漁民に対して,周辺にはFADを設置し,魚を集める代替手段として利用する地域も多い。クルング・ラヤ湾では,近い将来にはサンゴ礁のMPAを湾周辺にもうけて魚類資源を増やし,成長した魚類をFADで集つめて漁獲しようという計画をたてている。



