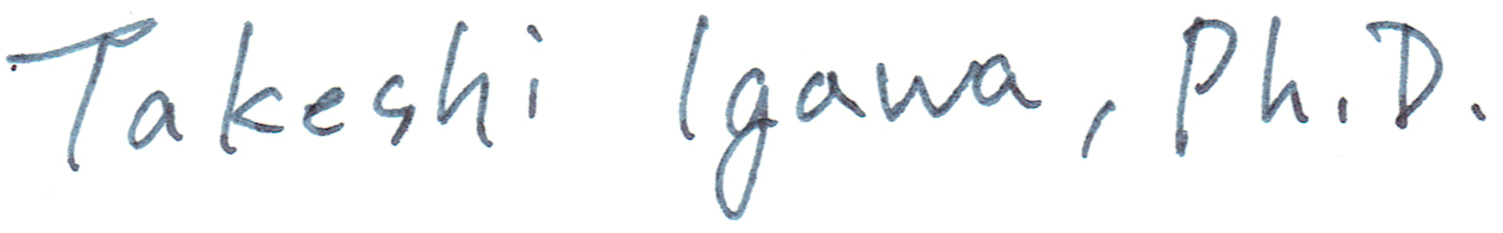論文解説:Robust molecular phylogeny and palaeodistribution modelling resolve a complex evolutionary history: glacial cycling drove recurrent mtDNA introgression among Pelophylax frogs in East Asia
Komaki S, *Igawa T, Lin S-M, Tojo K, Min M-S, and Sumida M. Robust molecular phylogeny and palaeodistribution modelling resolve a complex evolutionary history: glacial cycling drove recurrent mtDNA introgression among Pelophylax frogs in East Asia. Journal of Biogeography. 42:2159-2171 November 2015. [ DOI | http | PDF ]
本研究は、東アジアに産するトノサマガエル種群の、種間交雑の痕跡を含む複雑な進化史を分子系統学的アプローチによって解明した研究である。
本州の水田など身近な環境に生息するトノサマガエル(Pelophylax nigromaculatus)は、本邦だけでなく東アジア広域に産する。本州においては、同じような生息場所に別種であるトウキョウダルマガエル(P. prosus prosus)、ダルマガエル(P. prosus brevipodus)が生息しており、さらに、中国大陸においては、同様に、プランシーガエル(P. plancyi)が生息する。このようにトノサマガエル種群は多くの場所で即所的に別種が生息することが知られており、ヨーロッパなどでは、2種が交雑帯を形成して生息することが知られていた。東アジアについても、先行研究では中国大陸におけるトノサマガエルのミトコンドリアDNAが、過去の交雑によってプランシーガエルのもの置き換わっているとする報告があったが、核の遺伝子による系統樹による解析が不十分であり、間違っている可能性があった。
そのため、本研究では、これまでのミトコンドリア遺伝子に、核ゲノムにコードされる6つの遺伝子のイントロン領域を加えて頑健な分子系統解析を行った。さらに、サンプルの採集地点情報と、古気候モデルを用いて、分布域予測モデルを構築し、それぞれの種の氷期サイクルの分布域変動を推定することにより交雑が起こった原因を探った。
その結果、先行研究とは逆に、プランシーガエルのミトコンドリアゲノムがトノサマガエルのもと置き換わっていることが明らかになり、氷期におけるプランシーガエルの極端な分布域縮小によって、トノサマガエルのミトコンドリアゲノムが遺伝子浸透し、最終的に置き換わったものと推定された。また、日本産のトノサマガエルは、中国産トノサマガエルのミトコンドリアゲノムと、韓国産トノサマガエルの核遺伝子と近縁な遺伝子型を有していることが明らかになり、陸橋形成によって日本列島に流入する際に、日本列島の祖先集団は中国産と韓国産の掛け合わせによって誕生したことが示唆された。
以上の結果は、生物進化における複雑な歴史を明らかにしたものであり、ミトコンドリア遺伝子に依存したこれまでの分子系統学的研究に疑問を投げかけるものである。また、本研究は本邦産動物個体群において、初めて古代分布域予測モデルを用いた研究論文であり、今後、このようなアプローチによって生物多様性が生じる仕組みが解明されることが期待される。
本研究の成果は、当該分野において高い影響力を有する国際誌であるJournal of Biogeography誌に投稿し、掲載された。
著者:Komaki, S., T. Igawa(責任著者), S.-M. Lin, K. Tojo, M.-S. Min, and M. Sumida. 担当部分:実験計画、実験指導、解析、論文執筆を担当した。