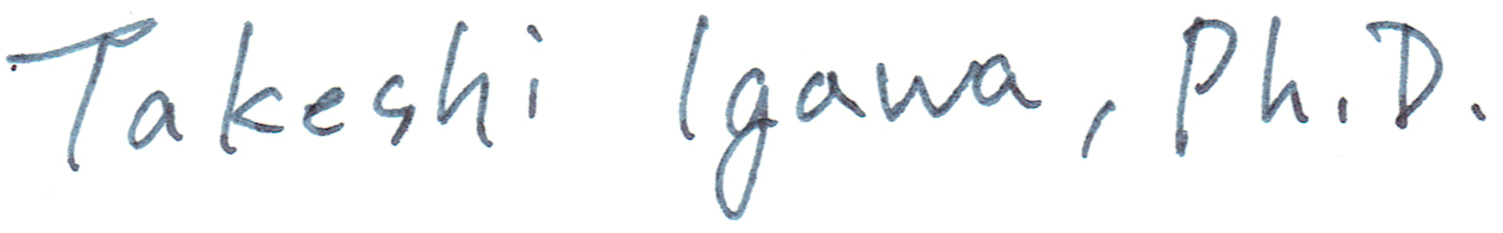[読書記録] 山田良純・広陵野球の美学
図書館の本棚をざっと見ているときに話題の文字が目に入ったので読んでみた。特に高校野球に興味はない。私の母校にはそもそも野球部がなかった。
1967年夏(第49回大会)の全国高校野球選手権準優勝と、2007年夏(第89回大会)の同準優勝のメンバーを中心に、決勝戦に至るまでの様相を聞き取り、まとめたもの。個々人の出自から来る野球に対する思いや、メンバー間の交流を描くことで長い歴史を持つ広陵高校硬式野球部の実像に迫ろうとしている。
1967年は私も誕生していない年代で、高校が今のイオンみゆき店あたりにあったことも知らなかった。宇品4丁目に叔母の家があり、ジャスコみゆき店としては思い出深い。練習中に水を飲むな、という非科学的特訓によって鍛えられたチームはこの時代の象徴だが、前評判の低かったチームは決勝戦へと劇的に進んで、その映像は映画にも使われたらしい。一方、2007年は何名かその後カープ球団に入団した選手がいたチームで、わりと想像がつく。監督も現在の監督であり、どのようなチーム作りが伝統としてあるのかも伝わってくる。興味深いのが、規律と自主性を重んじる指導方針である。宿舎内でズボンを腰パンにしていただけで、外出が禁止となり、その生徒が自主的に五厘刈りになるようなチームである(結局、2007年のチームも審判の微妙な判定もあって準優勝に終わっている)。ちょうど今問題になっている事象もそのような中で、チームのメンバー同士による規律の統制があって生じたのだろう。二つの時代で共通しているのは、高校野球と高校野球部という世間の価値観とは隔絶された社会である。世間ではコンプライアンスという名の下で、個人を尊重するために指導が非常にやりにくくなっている状況だが、高校野球において勝利を重ねるという明確な目標のために存在する高校野球部ではまた別の社会規範が存在してもおかしくない。
最近のパワーハラスメントとして取り上げられている事象の中には、そういった組織の中でのルールや分化が世間とずれていることによって生じているものが少なくないと思われる。しかし、世間とはなんであるのか、社会のルールとはなんであるのか、時代の空気間であると言ってしまえばそれまでなのだが、それがどのようにして形成されるのか一度、根本的に考えてみる必要がある。唯一明文化されたルールである法律についても同様である。人間の作り出すルールは時代によって移り変わる。暴力は罪であろう、しかし、教室で殴られていた我々はその時の教師を訴求したりしないのがその証拠である。そういえば、私は10代の頃からすでにそういったものの無常さ気づいていて、文系とよばれる分野に全く価値が見いだせないために、安易な進路選択をしなかったのを思い出した。
昨今の事件について個人的(組織を代表しない)見解を言えば、世間というただの雰囲気が作り出したルールと、一神教のような情熱的な文化が作り出した規範が乖離したために生じたものと結論出来る。ただただ不幸であるとしか言いようがない。