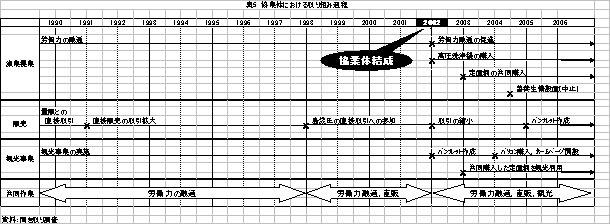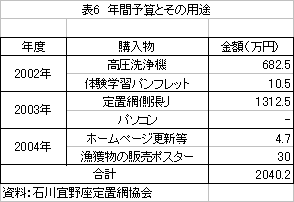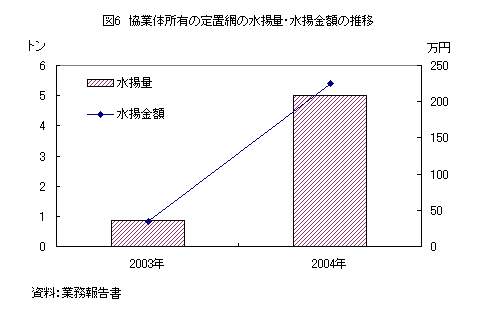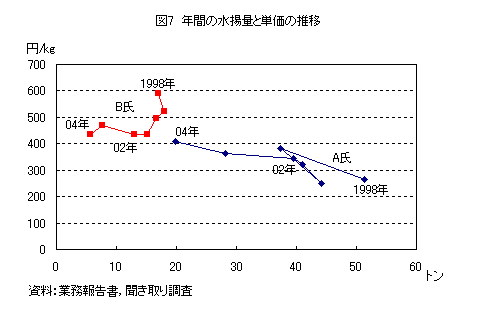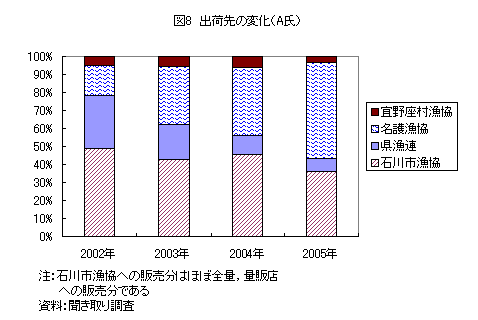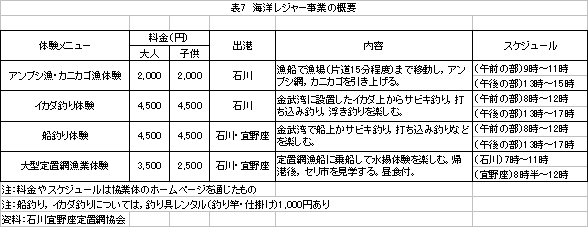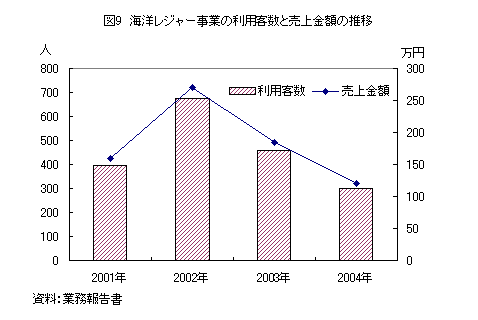| 5.協業体での活動内容とその成果 |
| 本協業体では,漁家経営改善のため下記のような取り組みを行っている(表5)。以下では,具体的な活動内容とその効果・課題について生産,出荷・販売,その他に分類して整理する。
なお,こうした活動にかかる費用は協業体事業の補助金(50%)と自己負担金(50%)によっている。事業の総額は約2,000万円であり,2002年は約700万円,2003年は約1,300万円,2004年は約35万円となっている(表6)。当初の計画では,2003年に共同購入・設置した大型定置網からの水揚金額の一部を協業体の活動資金として活用する予定であったが,水揚金額が低迷しているため実現していない。
|
|
|
|
|
1)生産 |
| 生産局面では海上作業,陸上作業ともに協業化の場面が見られる。海上作業では定置網の共同購入・設置,網替え作業時の労働力融通,海上作業では網洗浄機の共同購入,漁網修繕時の労働力融通を行っている。 |
(1)海上・陸上作業時の労働力融通
3グループともに雇用労働力を用いて定置網操業を行っているが,大漁時には労働力が不足,不漁時などには労働力が過剰となる。労働力が不足した場合,臨時に労働力を追加雇用して操業を行っていた。労働力を確保できない場合,網の修繕や網替え作業が滞り操業に支障をきたす場合も見られた。
そのため,大型定置網を営むA氏とB氏は,協業体を結成する以前から雇用労働力の融通を行うようになった。そして,協業体を組織したことによって経営体間の交流がより促進され,経営体間で人材を融通する場面が多く見られるようになった。当初は,労賃が支払われるケースもあったが,現在は労働力を相互に融通していることを理由に労賃は支払われていない。追加的な労賃を支払うことなく労働力を借り貸しする体制が整い,労働力不足によって作業が滞るケースは解消された。
こうして人材を融通することによって想定外の効果も見られる。そのひとつが漁業者間の技術交流である。経営体間の人材交流が進み,操業上の知識や技術を共有する場面が見られるようになった。具体例を挙げると,A氏は定置網操業中にロープが絡むことに苦慮していたが,B氏からロープの絡みを防止する工夫を学び,操業の効率性が向上した。さらに,A氏は網替え時,自ら雇用する労働力に加えて10名近くを臨時に雇用していたが,B氏から網上げの省力化の工夫を学び網替え時の必要労働力の削減を図っている。また,漁具の修繕に関する知識を有する乗組員がおり,漁具の修繕が必要な場合はその漁業者の知識を提供するなどして作業の効率化とコスト削減を図っている。
(2)網洗浄機の共同購入
定置網漁業で雇用労働力や労働時間を多く必要とする作業のひとつに漁網の洗浄がある。協業体を結成した2002年,労働作業の軽減化と省力化を目的に漁網の高圧洗浄機(総額682.5万円,性能:圧力35MPa,水量40リットル/分,エンジン45ps)を共同購入した。
高圧洗浄機の使用によって網洗浄作業の時間短縮が実現した。従来まで大型定置網の洗浄は3名~5名体制でひと月7日間程度,小型定置網の洗浄は2名体制でひと月3日間程度の時間が必要であった。網洗浄機の導入後は,大型定置網の洗浄は5名体制でひと月4日程度,小型定置網の洗浄は2名体制でひと2日間程度へと短縮された。
空いた時間は漁網の修繕や量販店への魚介類配送,海洋レジャー事業の対応などへ充てている。
(3)大型定置網側張りの設置
2003年,海洋レジャー事業の実施と定置網漁業からの水揚金額増加を目的に大型定置網の側張り(総額1,312.5万円,形式:親族型定置網本側張り300m×240m)を共同購入した。通常は漁業操業のために利用し,定置網観光の予約があるときは海洋レジャー事業のために利用している。定置網の耐用年数は8年と見込んでおり年間の減価償却費を164万円と計算している。
共同購入した定置網の運用は2003年12月から開始した。B氏の設営する大型定置網付近に設置したこともあり通常の管理はB氏が担当している。水揚金額の中から操業に必要なコスト(主にBグループの人件費)を差し引き,その残りをB氏とA氏で配分して共同購入した高圧洗浄機や定置網側張りの借入金返済に充てる。
運用を開始して約2年になるが,漁家経営の改善へ寄与するほどの成果はあがっていない。相次ぐ台風の接近による操業中止,全体的な資源悪化などのため年間水揚金額は低位にある。2004年の水揚金額は約225万円,2005年はさらに下回る見込みである(図6)。定置網観光の売上金額30万円から50万円を合計しても,年間売上金額は260万円から280万円ほどである。定置網の減価償却費(年間164万円),人件費,燃油代,漁網の修繕費などを差し引くと,最終的には利益はほとんど残らない。
|
|
|
2)出荷・販売 |
| 出荷・販売局面では,蓄養生簀の共同購入・設置(中止),量販店への共同出荷,魚介類のPR活動などに協業化の場面が見られる。 |
(1)蓄養生簀の設置
大漁時の値崩れ防止,不漁時の高価格出荷,量販店への安定供給などを目的に,それぞれが大型定置網設置海域付近に蓄養生簀を設置している。ただ,荒天時には蓄養生簀の設置海域へ行くことができず出荷不能となる。
そのため2004年度内に蓄養生簀を5基共同購入して石川市漁港内に設置する計画であった。しかし,2002年以降,水揚量が大幅に減少しており,蓄養するだけの魚介類を確保できないと判断して購入計画を中止した。
(2)漁獲物の販売方法の工夫
水揚量が大幅に減少する中で,漁獲した魚介類の高値販売を目指したふたつの取り組みが実施されている。こうした取り組みなどによってA氏の販売単価は若干の上昇,B氏の販売単価は横ばいといった状況にある(図7)。
|
|
|
① 量販店への共同出荷の実施
ひとつは量販店との直接取引の実施である。石川市漁協と量販店との直接取引は1980年代に始まった。当初は,定置網から魚介類を水揚げした後,漁協職員らが現物を持って石川市内の量販店や鮮魚店へ売り込むという「行商的」な販売方法であった。量販店側から見ると市場を経由するよりも鮮度の良い魚介類を確保できる点が魅力であり次第に取引を拡大した。1991年前後からは,量販店の本部を通じて石川市のみならず当該量販店の全店舗へ供給するケースも見られるようになった。
こうした販売活動を知ったA氏は宜野座村漁協でも同様の取り組みを行いたいと考えるようになった。石川市漁協の職員に相談を持ちかけたところ,量販店との直接取引には安定供給や煩雑な交渉などが必要であり簡単ではないことを知った。こうしたことからA氏は,1998年より煩雑な量販店との交渉を石川市漁協に任せ,石川市漁協からのオーダーに基づいて漁獲物を販売するようになった1)。量販店への販売価格の下限は200円/kg(送料込)を基準としており市場出荷よりも価格的にかなり有利なケースも見られることから2),A氏は全水揚金額の40%から50%相当の魚介類を石川市漁協を通じて販売している(図8)。
石川市漁協にとっても量販店へ漁獲物を安定供給するためには海域の異なる定置網を確保することが有効であり,A氏から魚介類の供給を受けることで量販店との取引に欠かせない安定供給体制を強化できるというメリットを得ている。
その後も量販店との取引は拡大し,各経営体は蓄養生簀を定置網付近の海域に設置して安定供給体制の確立を進めた。量販店との価格交渉では,市場を経由するよりも鮮度の良い魚介類を提供可能であること3),安定供給に応えるために蓄養生簀を設置するなどのコストをかけていることなどを理由に,販売価格の下限を200円/kg(送料込み)としている4)。1日あたりの出荷量は通常100kg~400kgであるが,広告掲載時には500kg~1トンの魚介類を出荷する場合もあった。ただ2002年以降,漁獲量の大幅減少に伴って量販店との取引金額も減少傾向にある。
|
|
|
【例】量販店との取引例
量販店への販売の中心を占めるK社との取引システムを例示する。K社は沖縄県における大手量販店のひとつであり60店舗ほどを展開している。
まず石川市漁協がK社からおおよその注文を受ける。新聞などへの広告を掲載する場合は10日ほど前にその内容を漁協に伝える。その注文に石川市漁協がA氏とB氏から漁獲物の情報を収集してそれぞれに発注をかける。K社が魚介類の宣伝広告を行う場合は,その注文に確実に応えるために数日前から蓄養生簀へ漁獲物を蓄養する。
そしてA氏やB氏が西原町にあるK社本部へ配送したり,K社の担当者が集荷に来たりした。2002年ごろからは,石川市から約1時間半の距離にある糸満市の業者へ配送するシステムとなった。輸送費などのコストは1回3,000円程度であり,漁業者が負担している。
近年はK社から店舗ごとの注文書をとり,店舗ごとに分荷して糸満の業者に納めている。K社にとっては分荷する手間が省け,漁業者にとってはその手間を理由に販売価格の下限を設定している。
② エサとして販売
もうひとつは,大漁時に漁獲物を冷凍保存してエサとして販売する方法である。量販店と取引することによって大漁時でも一定量の魚介類を200円/kg以上で取引することが可能になったが,大漁時には量販店からの注文を遙かに上回る水揚量があり,それらを市場出荷すると販売単価が50円/kg前後にまで下落する場合も少なくない。
こうした場合,石川市漁協の冷蔵庫へ冷凍保存してエサとして販売している。エサの販売価格は200円/kg以上を目標としており,多くが150円~200円程度で取引されている5)。200円/kgで販売した場合,梱包費用や冷凍庫使用料などを除くと170円/kg~180円/kgになり,大量時に市場出荷する場合に比べて高値である場合が多い。なお,エサとして冷凍・販売する主な魚介類は,ムロアジ,イワシ,グルクマ,小型のカツオ,メアジ,小型のエビなどである。
定置網の漁獲が良好であった頃は年間10トン近くをエサとして販売していたが,漁獲量減少に伴ってエサとして販売する量も減少している。2004年は約2トン,2005年はほぼゼロである。
エサの注文・販売は石川市漁協が行っている。石川市漁協に所属するマグロ一本釣り漁業者からは大型イワシ,タチウオ曳縄釣り漁業者からは小型イワシの需要が多い。この他にも,魚類養殖を営む漁業者を抱える漁協から注文が入る6)。
(3)魚介類のPR活動
2005年,沖縄産の新鮮な魚介類であることをPRすることを目的にしたポスターを作成(総額30万円)して取引関係にある量販店へ配布した。また近年,魚介類の調理方法を知らない消費者が増えていると感じており,調理方法を記載したパンフレットも配布している。 |
3)その他-海洋レジャー事業-
近年,修学旅行や総合学習のメニューとして海における観光活動に注目が集まっている。適切な集客・宣伝を通じてこうした需要に対応できれば新たな収入源を確保することにつながると考え,A氏は定置網観光,B氏は定置網観光と船・イカダ釣り,C氏はアンブシ漁とカニカゴの体験事業を行っている(表7)。
|
|
|
| 協業体結成以降も個別に海洋レジャー事業を行うことに変わりはないが,それぞれの事業を一括に紹介するパンフレットを作成(総額10.5万円)して宣伝活動に力を入れている。2003年には協業体で大型定置網を共同購入・設置し,漁船を用船しあうことによって修学旅行生などの団体客へ対応している。2004年2月にはホームページを開設して海洋レジャー事業のPR活動を行っている(A氏が管理を担当)。ただ,2005年11月現在までのアクセス数は約800であり,ホームページを通じた申込件数も2件程度に留まっている。
大半の利用客が恩納村体験学習研究会ニライカナイ(以下,ニライカナイ)を介して訪れている。ニライカナイは1998年,恩納村に設立された有限会社であり,農業や生活,文化,自然,漁業の5分野33種目,84プログラムの体験学習を提供している。ニライカナイが予約を受け,予約内容に基づいて石川市漁協へ海洋レジャー事業の実施を依頼している。石川市漁協へ定置網観光の依頼が入った場合,同漁協に属するB氏へ依頼する。予約人数が多い場合やB氏の定置網が網あげしている場合はA氏へも依頼する。協業体所有の定置網を案内する場合はA氏とB氏を中心に対応する。船釣りやイカダ釣り,アンブシ漁などの予約が入った場合はB氏やC氏が対応している。
利用客の中心は高校生であり,一般客の利用はほとんどない。修学旅行の一環として訪れる県外の高等学校,地元の高等学校による職業体験として訪れるケースが大半を占める。年間の利用客数は,2001年396名,2002年675名,2003年460名,2004年300名である。船釣りやイカダ釣りの利用者が全体の9割近くを占めている(図9)。
料金設定は協業体経由と漁協経由とで異なる。協業体の海洋レジャー事業のスケジュールは漁業操業の時間帯にあわせたものであり別表のような料金設定となっている。漁協を通じた海洋レジャー事業のスケジュールは利用客の都合に合わせて実施するため料金は若干高く設定されている。利用客の平均単価は4,000円であり,年間の売上金額は2001年約160万円,2002年約270万円,2003年約180万円,2004年約120万円である。漁協には手数料として2002年60万円,2003年30万円,2004年25万円の収入がもたらされている。
漁協や協業体では今後も海洋レジャー事業に力を入れたいという意向をもっている。
|
|
|
|
|